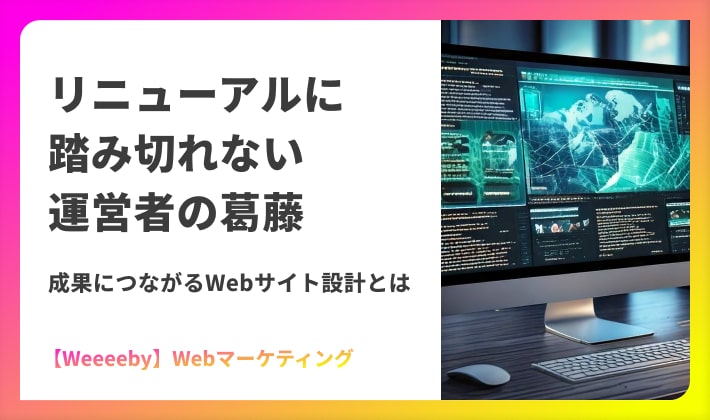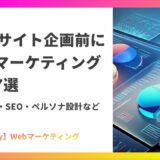Webサイトのリニューアルに踏み切れない。
少しだけPVがあるから、消せない。でも今のままでは、成果が出ない。
これは、個人メディア運営者なら誰もが一度は抱える葛藤かもしれません。
本記事では、数字では割り切れない“残したい気持ち”と、効果を生む設計視点について考えます。
この記事でわかること
- Webサイトのリニューアルに踏み切れない理由と、運営者が抱える“葛藤”の正体
- PVや滞在時間などのデータをもとに、削除ではなく“設計”で活かす運用視点
- クライアントの声から学ぶ、効果的なWebサイト改善のヒント
リニューアルに踏み切れない理由は「気持ち」だった
Weeeebyを立ち上げてから、ずっと目指してきたのは「成果につながるメディア」。
しかし、WebサイトのPVが伸び悩み、成長が止まっているように感じる中で、方向性や構成を見直すべきか何度も悩みました。
なのに「なぜかリニューアルに踏み切れない」その理由には、データだけでは判断できない“ページを残したい気持ち”にありました。
「このページは、ちゃんと読まれている」
そんな感覚が、成果とは別の価値を感じさせていたのです。
さらに、“折角作ったページだから残したい”という「もったいない気持ち」も、判断を迷わせました。これは、私だけでなく、クライアントもよく口にする感情です。
「誰かが見てくれているなら、残したい」そんな声に、Web制作者・運用者としてどう向き合うのか。その答えを探すことが、リニューアルの本質なのかもしれません。
PVデータを見て、迷いが深まった
直近30日のGoogleアナリティクスを見てみると、PVが少しある(50PV以下)記事が、いくつも並んでいました。
- キャッチコピー参考サイト一覧
- FAQで使える例文集
- トップへ戻るボタンのレイアウト など
どれも、誰かが見てくれている。
それだけで、「消すのはもったいない」と思ってしまう。
でも、滞在時間は短く、直帰率も高い。
ユーザーからの直接的な反応には結びついていない。
これまで私は、企業のWebサイトのリニューアルや運用を担当していましたが、こうしたページは「整理対象」として扱われます。KPIに基づいて、PVやCVに貢献していないページは、構成見直しや削除の候補になるのが一般的です。

しかし、実際に自分がWebメディアを作ってみると、数字だけでは割り切れない感覚があることに気づきます。
- 少しでも読まれているなら残したい
- 誰かの役に立っているページかもしれない
そんな気持ちが、冷静な判断を揺らがせるのです。
結果を出したい一方で、ページに込めた想いや制作にかけた時間が、判断を難しくしていました。これは、個人でも企業でも、運用者なら誰もが一度は経験する“葛藤”かもしれません。
この「想い」に寄り添うことが、Webサイトのリニューアルや運用において本当に大切なのだと気づきました。
クライアントの言葉がよみがえった
「数字に現れない感覚がある」それは、自分がWebメディアを運営して初めて実感したものでした。
ある案件で、クライアントから「このページ、誰かに届いてる気がするんです。消したくないんです。」と言われたことがあります。
当時の私は、企業のWeb運用担当として、最終的には「数字」で判断しました。
PVやCVに貢献していないページは「構成の見直しや削除の候補になる」それが“正しい判断”だと信じていました。
でも今なら、その言葉の重みがわかります。
“誰かに読まれている”という感覚は、数字では測れない。
それは、本気でサイトと向き合ってきた運営者だからこその“言葉”であり、クライアントの“想い”でした。
Webサイトの運用は、数字と感情の間で揺れるもの。
その両方に目を向けることが、効果的なWebリニューアル・サイト運用の第一歩なのだと、今は思います。
削除ではなく“設計”という考え方に変わった瞬間
数字では測れない“残したい気持ち”を、成果につなげるにはどうすればいいか。
そう考えたとき、見えてきたのは「消すか残すか」ではなく、「どう活かすか」という視点でした。
- PVがあるなら、導線を見直す
- 滞在時間が短いなら、構成や事例を追加する
- CTAがないなら、収益導線を設計する
つまり、コンテンツは“削除”ではなく“設計”で育てるもの。
この視点に切り替わった瞬間、ようやく“運用者としての覚悟”が生まれました。
Webサイトを“育てる”という視点へ
「リニューアルに踏み切れない」
それは、Webサイトを運用する多くの担当者が抱える葛藤です。
しかし、Webサイトを“育てる”という視点が、リニューアルに迷う運営者の葛藤を解きほぐす鍵になります。反応が薄いページに、「消すべきか」「残すべきか」で迷う。でも本質は、「残すか消すか」ではなく、“活かし方を設計する”という視点にあるのだと、今回の気づきで実感しました。
Webサイトは、ただ情報を発信するだけの場ではありません。
ユーザーの行動や感覚に寄り添い、価値ある情報を届ける“設計型メディア”です。
数字だけでなく、読者の感覚や現場の声に耳を傾けながら、コンテンツを育てていく。
この視点こそが、運営者・制作者・クライアントに共通する“効果的な改善へのステップ”になるでしょう。
制作者から運営者へ、視点が切り替わった理由
この気付きを得るまで、私は“制作者”としてWebサイトを作ってきました。でも、PVや滞在時間・読者の行動を分析し、構成を見直すようになって、ようやく“運営者”としての視点と責任を持てるようになりました。
そして今でも、あのクライアントの言葉「誰かに届いてる気がする」が胸に響いています。
本記事にある葛藤は、多くのWeb担当者や個人メディア運営者にもきっと共通するもの。
だからこそ、“成果につながる設計”という視点を言語化し、この記事に込めました。
誰かの「行動のきっかけ」になれば嬉しいです。
Webサイトのリニューアル・運用でよくある質問(FAQ)
PVが少ないページは削除すべきですか?
一概には言えません。導線や構成を見直すことで成果につながる可能性があります。
リニューアルの判断基準は何ですか?
PV・滞在時間・CVなどのデータに加え、運営者やクライアントの意図も重要です。
Webサイトを“育てる”とはどういう意味ですか?
設計視点に基づき、目的達成を目指してサイトを効果的に育てていくための運用方針です。